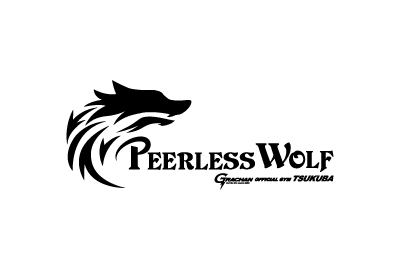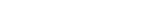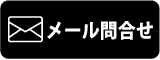「関節の痛みが出たときの正しい対処法」理学療法士が教える、トレーニングに戻るまでのステップ
トレーニングやスポーツをしていると、突然関節に痛みが出たという経験がおありの方も多いかと思います。

「少し我慢すれば治るだろう」と放置してしまう人も多いですが、間違った対応をすると回復が遅れたり、慢性的な痛みに移行してしまうこともあり注意が必要です。
今回の記事では、理学療法士としての視点から
関節に痛みが出てから安全にトレーニングへ復帰するまでの流れを、皆様にわかりやすく解説していきたいと思います。
関節に痛みが出た際に、理解しておくべき要点は次の5つです。
1.急に関節が痛くなったときの対処法を理解する
2.痛みの原因を見極める
3.急性期(発症直後)の正しい対応
4.痛みが落ち着いてきたらやるべきこと
5.元のトレーニングに戻るためのステップを理解する
1. 関節が痛くなったとき、まず行うべきこと
痛みが出た直後は「無理をしない」が鉄則です。
そのまま動き続けると、炎症や組織損傷を悪化させる可能性があります。
急性期では「RICE処置」を行います。

RICE処置とは?
急性期的に起きた怪我や炎症に対して行うべき処置
迅速に4つの処置を行うことでケガによる痛みや炎症を最小限に抑えることが可能です。
Rest(安静):痛みのある部位を使わないようにする。歩けない方は松葉杖などを使用
Ice(冷却):患部を15〜20分を目安に冷やす(受傷後48時間ほどは1~2時間おきに繰り返す)
Compression(圧迫):軽く圧をかけて腫れを防ぐ(受傷後24~48時間はできるだけ頻繁に)
Elevation(挙上):心臓より高く上げて腫れを抑える(受傷後48時間はできるだけ常時)

これらは怪我の箇所や程度によっても異なり、全てを必ず行わなくてはいけないということではありません。
状況を的確に判断して判断していくことが大切です。
2. 痛みの原因を見極める
関節の痛みといっても、原因は様々です。
・関節内の炎症
・筋肉や腱の損傷
・神経痛
「どの場面で痛めたのか?」「どの動きで痛いか」「どんな種類の痛みなのか?」を明確にすることがとても重要です。

例えば、膝の痛みなら「しゃがむ」「階段を降りる」「ジャンプする」など痛みが出る場面や、具体的な動作や痛みの種類(ズキズキする・重い感じの痛みなど)を記録しておくと原因特定に役立ちます。
痛みの原因によってもその後の対処は大きく異なります。
原因をきちんと把握した上で、その後の向き合い方を決めていくことが大切です。
3. 急性期(発症直後)の正しい対応
発症から48〜72時間は、炎症が強く出る時期です。
この時期は「安静と冷却」が中心。
上記でご説明したRICE処置が基本となります。
無理にストレッチやマッサージを行うと悪化する場合もあるので注意が必要です。

ただし、全く動かさないと関節だけでなく周囲の筋肉や靭帯などの動きが悪くなってしまうこともあるため
痛みのない範囲で軽く関節を動かし、柔軟性を保っておくことも大切です。

状況を的確に把握し、やれること・やれないことを的確に判断して実行していくことがこの時期には必要になります。
4. 痛みが落ち着いてきたらやるべきこと①関節可動域の確保
炎症が徐々に治まり、痛みが落ち着いてきたころ
「運動を早く再開したい!」という気持ちはわかりますが、焦ってはいけません。
関節に痛みが出た後には、筋肉のこわばりや動かなかったによる関節周囲の軟部組織の柔軟性が低下しているケースが少なくありません。
この時期には少しずつ関節を動かし、可動域(動く範囲)を取り戻していくことが重要です。

ここでのポイントは段階的に、痛みの出ない範囲から行うこと
決して無理をしないようにしてください。
関節可動域確保へのアプローチは、以下の通りです。
①自分の筋力を使わずに外からゆっくりと動かしてもらう。
②反対の手、タオルなどを使いサポートをしながら自分の筋力も使ってゆっくりと動かす
③自分の筋力でしっかりと関節を動かす

炎症が残っている場合には、初めから自分の筋力で関節を動かそうとすると、
炎症が悪化したり再損傷を引き起こすことがあります。
関節を動かしていくタイミングは、痛みの原因によっても異なるため
医師の判断を仰いだり、理学療法士などの専門家に相談をしていただくことも大切です。
痛みが落ち着いてきたらやるべきこと②筋肉の再教育
痛みがある間は無意識に動きをかばってしまうため
筋肉と神経の連動が乱れてしまうケースが多くみられます。
わかりやすく言うと、痛みが取れた後に動きに不器用さが残ってしまうということです。

このような状況下では、弱くなった筋を再び正しく使えるように
神経と筋肉の再教育を行うことが大切です。
膝関節なら大腿四頭筋の再活性化

肩関節なら肩甲骨周囲筋の安定化トレーニングなどを適切な指導の下行います。

痛みが取れた→「すぐに元通りのトレーニング」という考え方をしてしまうと
動きをうまくコントロールできず、効果的なトレーニングができなかったり、痛みを繰り返してしまう原因にもなります。
トレーニングへ復帰するための準備期間とも言えるこの時期
しっかりと神経と筋肉の連動性を高めることが重要です。
5. 元のトレーニングに戻るためのステップ
痛みなく日常生活が送れるようになり
関節の可動域も回復していると感じられるようになれば、徐々にトレーニングへと復帰していきます。

ここでは、膝関節の痛みが出た場合のトレーニング再開へのプロセスを、自分のトレーナーとしての経験も踏まえてお伝えしていこうと思います。
基本的なステップは以下の通りです。
①低負荷、狭い範囲の運動から開始
例:膝の軽い屈伸
②荷重を徐々にかける
例:両脚でのスクワット → 片脚でのスクワット
③動きの範囲を広げていく
例:浅いスクワット → 深いスクワット
④自由度の高い運動へ(不安定化での運動)
例:ランジ、ステップ動作、ジャンプ動作など
⑤負荷を高める
例:ウエイトを使った筋力トレーニングやスポーツ動作へ復帰
一般的には「小さい動き → 大きい動き → 複雑な動き・高負荷のトレーニング」の順番で負荷と可動域を調整していくことが、安全にトレーニングへ戻るための基本です。

しかし、人間の身体の反応は非常に複雑であり、現場ではマニュアル通りに進まないことの方が多いと感じています。
ここからは、私自身がトレーナーとして現場で感じていること、実践している内容を中心にお伝えしたいと思います。
「不安定な環境下でのトレーニング」の重要性
特にピアレスウルフで重要視しているのは
不安定な環境で関節の動きをコントロールすること
片足立ちや

バランスディスクを用いたトレーニング

これらを行っていくことで、関節の動きをコントロールできるようになることが
トレーニングにおける痛みの再発防止・予防の観点から非常に重要であると感じています。
これは日常生活で起こる関節の痛みの予防・改善に対しても同様で
「関節の安定性を高める」上で不安定な環境下でのトレーニングは非常に有効です。
回復への道は一人一人異なる。
痛みが出てから、通常のトレーンングへ復帰するまでのプロセスは一人一人大きく異なります。
基本のプロセスを知ったうえで、状況に合わせて柔軟に対応していくことが重要です。

「トレーニング中に痛みが出てしまった」「どうしたらよいかわからない」などのお悩みがある方は
公式ラインからお気軽にご相談ください。

最後まで読んで頂きありがとうございました!
記事の執筆者
阪本洋平(ピアレスウルフ代表)
・理学療法士
・総合格闘家/初代GRACHANライト級チャンピオン/第二代GRACHANフェザー級チャンピオン
・パーソナルトレーナー
経歴
琉球大学理学部海洋自然科学科生物系卒業。
琉球大学在学時代から総合格闘技のプロ選手として活動を開始。
その後自らの怪我や痛みの原因を知るため、茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科に入学。
在学中も選手としての活動を継続する。
卒業後は理学療法士として茨城県内の総合病院に勤務する傍ら、初代GRACHANライト級チャンピオン(2016年)第2代GRACHANフェザー級チャンピオン(2017年)を獲得。
2023年4月、つくば市松代にキックボクシング・ブラジリアン柔術・総合格闘技ジム「ピアレスウルフ」パーソナルトレーニングジム「ピアレスウルフパーソナル」をオープン
阪本典子(スペシャルアドバイザー)
・医学博士
・大阪市立大学 医学研究科解剖学 博士課程修了
・九州栄養福祉大学 名誉教授
・近畿大学医学部 学内講師